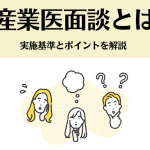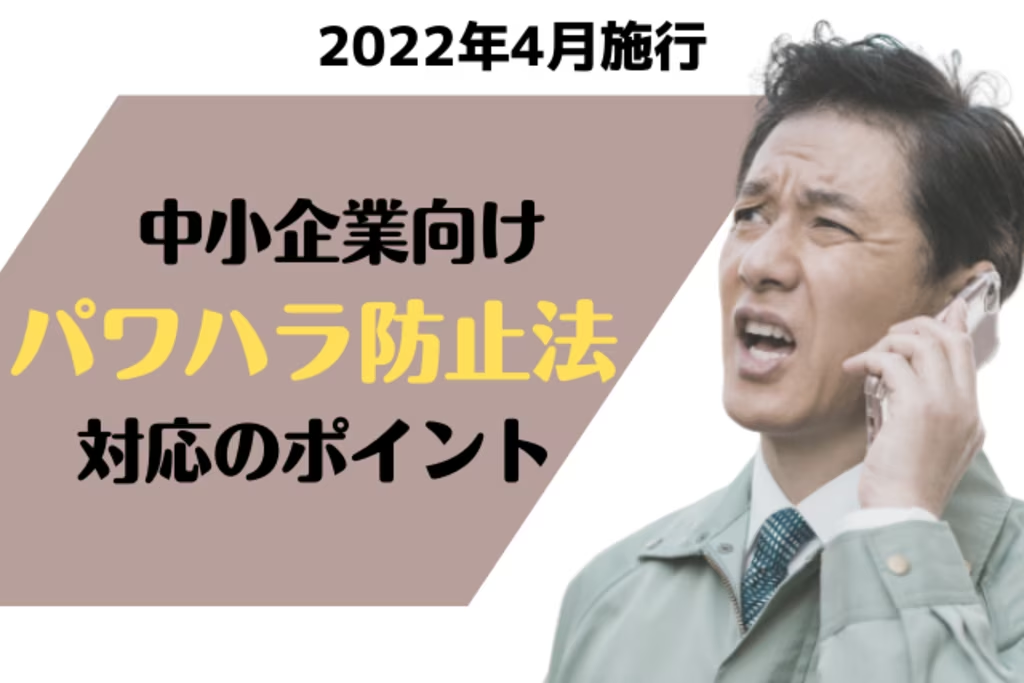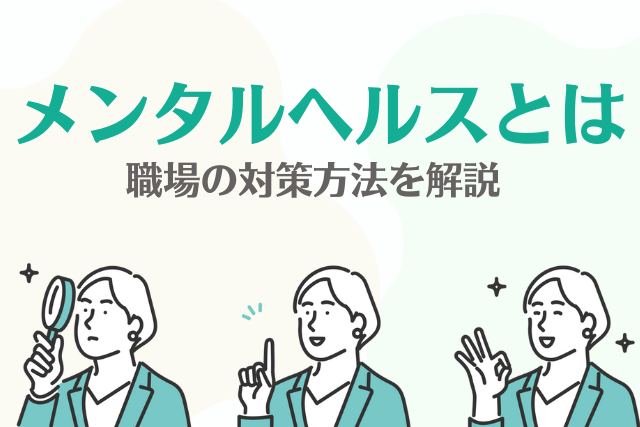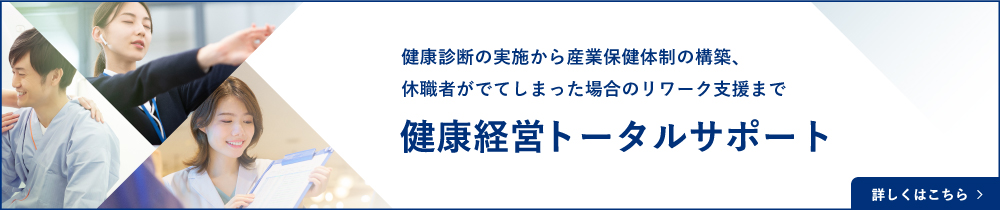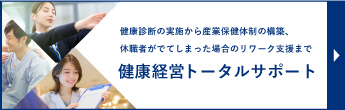〈セミナーレポート〉産業保健師が解説!企業担当者がメンタルヘルス不調者対応で気をつけるべきポイントとは?
サンポナビ編集部
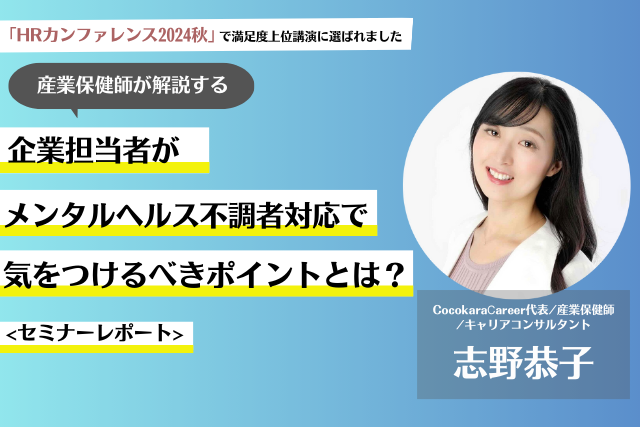
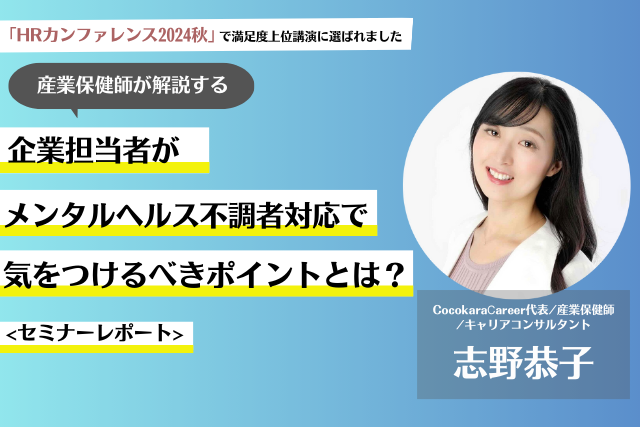
2025年2月、産業保健サービスを提供する株式会社エムステージは、オンラインセミナー「産業保健師が解説!企業担当者がメンタルヘルス不調者対応で気をつけるべきポイントとは?」を開催しました。
講師は、10社以上の企業、健康保険組合で活動されている産業保健師の志野恭子氏。メンタルヘルス不調の早期発見から休職・復職時の対応まで、具体例を交えた講義が行われました。
約250名のご参加、200件超のアンケート回答のうち、97%の方に「満足」「非常に満足」とご回答をいただいたセミナーの内容をレポートします。
目次
「不調を生まない職場環境づくりを」メンタルヘルス不調の予防策
企業担当者の方から、よく「不調者が減らない」「早期発見が難しい」「休職後の復帰に不安がある」といった相談を受けます。日々発生するメンタルヘルス不調者の対応に追われているかと思いますが、最も重要なのは「不調を減らす取り組み」です。
職場の人が原因で起こる環境の悪化が、メンタルヘルス不調者を発生させる要因になっています。予防のためには、ご自身の職場環境をしっかり見直して、改善に取り組むことが重要です。
メンタルヘルス不調が発生しやすい職場には、以下のような特徴があります。
|
まずは、ご自身の職場環境を見直し、社員の意見を取り入れて改善に取り組むことが重要です。
また、上司との関係に悩んでいる従業員は非常に多く、その関わり方は部下のメンタル不調予防に大きく影響します。上司が以下のような点に気を配れると、メンタルヘルス不調の予防につながるでしょう。
|
特に、部下のメンタルヘルス不調に気づくには「雑談力」が重要です。部下の考え方や生活、プライベートなどを自然な雑談の中で引き出せると、メンタルヘルス不調に気づきやすくなります。ただし、そのためには上司自身も心の余裕がないと難しいため、管理職のセルフケアも大切です。
上司の関わり方に加え、組織風土の改善やメンタルヘルス・ハラスメント教育の体制整備など、社員が働きやすい職場づくりを日頃から行うことが大切です。特に、入社時に以下のような点を丁寧に説明しておくと、従業員が自発的にメンタルケアを行う意欲が高まり、予防につながるでしょう。
|
「休職の一歩手前で気づくのは遅い」早期発見と早期対応のポイント
メンタルヘルス不調の早期発見には日常の中に潜む「SOSサイン」に気づくことが大切です。例えば、以下のような様子の社員がいたら、ひとまず声をかけて話を聴く姿勢を示して相手の反応をうかがってみましょう。
- 昇進したが責任が重く不安が強い
- 同じミスを繰り返して自信をなくしている
- 仕事と家庭のバランスが難しく、毎日がつらい
特に、次のような兆候がみられる場合、メンタルヘルス不調が疑われるため、産業医など専門家に相談することをおすすめします。
|
休職の一歩手前で気づくのではタイミングとしては遅いといえるので、早めに対応できるよう相談のハードルを下げることも重要です。相談窓口を複数用意し、使い方や効果を十分に周知し、相談しやすい環境づくりを意識しましょう。
そして、専門家への相談が必要なケースがあれば、早めに連携することが重症化の予防につながります。ただ、企業担当者の方の中には、「メンタルヘルスに関連する不調に詳しくないけれど、勝手に判断して相談につなげてもよいのか」と迷う人もいるでしょう。
そこで理解していただきたいのは「疾病性」と「事例性」の違いです。疾病性は、症状や病名など専門家が判断する分野、事例性は職場で問題になっている事象を指します。
企業としては、事例性に目を向け、「安全かつ健康的に働ける状態なのか」を検討する対応が望ましいでしょう。そして、必要に応じて医療機関への受診を促したり、産業医や保健師につないだりすることが企業担当者の主な役割となります。
「休職期間をどう過ごすかが大切」休職・復職対応のポイント
休職時の診断書が提出された際は、休職に至った原因を十分に確認することが大切です。診断書に症状や詳細な原因が記載されていない場合は、信頼関係のある上司や産業医が確認しましょう。聴取した休職理由をもとに、企業として復職後の再発防止策を準備します。
また、休職者への説明も丁寧に行いましょう。休職した直後は、意欲が低下しており、自分で休職手続きや就業規則を調べるのが休職者にとって負担となります。そのため、「休職ハンドブック」のような冊子をつくり、書面で伝えるとよいでしょう。
休職ハンドブックには、次のような情報を盛り込みます。
|
また、休職期間をいかに過ごすかが復職後の再発予防では大切です。休職は復職が前提の療養であることを意識し、ただ休むのではなく従業員が休職原因に向き合えるようなサポートが必要となります。カウンセリングや認知行動療法、リワークの活用、家庭問題の解決などを企業として支援しましょう。
続いて、復職対応では診断書が出される前の事前準備が重要です。診断書提出までに本人と面談し、次のポイントを話し合っておくと対応がスムーズです。
- 復職プログラムの説明
- 復職診断書に記載する事項の説明(就業上の配慮が必要なら主治医に記載してもらう)
- 企業として配慮できる・できない点
- メンタルヘルス不調の原因に対策ができているかを確認
復職後の再発防止のポイントは「焦らないこと」です。本人の症状が就業できる水準まで回復していない場合や、再発予防の対策ができていない場合は、復職時期を延期する対応も必要です。
復職時点の回復状況は100%ではなく、多くの場合は70%程度と考えられています。また、数か月~5年程で再発する可能性もあります。再発リスクを念頭に置いて対応すると、復職プログラム通り進まなくても焦らず対応しやすいでしょう。
中途採用者、若手社員、新型うつ…ケース別の対応
メンタルヘルス不調の対応で、特に注意が必要なケースについて紹介します。
中途採用者:教育体制の配慮と相談しやすい環境づくりが大切
中途採用者のメンタル不調の原因として「わからないことを聞きにくい」点が挙げられます。前職の経験が必ずしも通用するとは限らず、企業文化や業務の違いに戸惑いがちです。一方で、企業からは即戦力としての活躍を期待されるため、力を発揮できないことに落ち込んでしまうのです。
中途採用者が業務で困らないよう、企業理念や業界用語、社内用語、独自ルールなどをあらかじめレジュメにまとめて渡すとよいでしょう。
また、同期入社が少なく、人間関係を築く機会が少ない点もストレスの原因となります。「同年代や他部署の社員の交流機会を増やす」「定期的な面談を行う」など、孤立を防ぐためには、入社後すぐの丁寧な対応がカギになります。
若手社員:若者の価値観に寄り添って必要性を伝える
若手社員は、これまでの世代とは異なる価値観や考え方を持つため、若者の特徴を理解したコミュニケーションが求められます。例えば、若手社員の特徴として以下が挙げられます。
- SNSやチャットなどライトなコミュニケーション中心で直接の会話が苦手
- 理不尽なことを嫌う
- コスパ・タイパ重視で無駄なことをしたくない
業務指示を行う際には、目的や必要性、本人にとってのメリットを伝え、腹落ちしてもらうことが大切です。育てることを諦めず、褒めたり励ましたりする関わりを中心に、コミュニケーションを工夫しましょう。
新型うつ:本人のつらさに共感的態度で接する
新型うつとは、従来型のうつと異なり、「仕事では抑うつ的になるが、プライベートでは元気に活動できる」といった特徴があります。若年者に多く、比較的軽症のことが多いものです。
自分を守るため、周囲に攻撃的になりがちです。一方で、本人は非常につらいと感じているため、否定せず共感的に話を聞くことが大切です。また、過眠や不眠など、生活リズムが不規則なケースが多いため、規則正しい生活を送るよう指導しましょう。
心療内科・精神科を受診してもらう際のために、会社から社員に推薦できるクリニックを用意しておくと良いでしょう。オンライン診療で「初診で即日診断書発行」など、すぐに休職が必要な状態か疑わしいケースもあります。
個別対応を求める社員:安全配慮義務の観点から慎重で丁寧な対応を
休職や復職時に個別の対応を求める社員がいるケースもあります。例えば、「休職時も給料を支払ってほしい」「復帰後はテレワークをしたい」「診断書は出したくない」などです。
基本的には、就業規則の範囲内で対応し、特例対応を避けることが大切です。特例対応をしてしまうと、他の従業員からの不満につながります。
それでも納得しない場合は、安全配慮義務の観点から慎重で丁寧な対応を心がけます。面談時の記録をしっかり残しておき、早めに社労士や弁護士に相談しましょう。
まとめ
|
セミナー参加者から寄せられた感想

半年前に職場異動で着任してから、産業保健分野に携わるようになり、休務者対応の担当になったのですが、このような研修を受講できずに過ごして参りましたため、伺いたいポイントが非常にまとまっており、大変勉強になりました。

部下の体調不良にはなるべく関わらない(接し方がわからない)管理職も見受けられるので、安全配慮義務の観点からも管理職に対する教育・研修も必要だと感じました。

休職者の対応について全社的に取り組んでいく必要があると改めて感じました。不調の申し出があった後の対応も重要ですが、まずは申し出がある前にチームで会社で防止できるよう努めていきたいと思います。
・
・
・
株式会社エムステージでは、ストレスチェックツールやメンタルヘルス研修、復職支援プログラムなど、メンタルヘルス対策に関するサービスを提供しています。メンタルヘルス不調者の対応にお悩みの方はお気軽にお問合せください。

 ログイン
ログイン